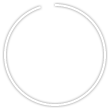nav
aside
超高層住宅
塔としての住居
一般に、20階以上の集合住宅を超高層住宅と言う。2005年以降に完成予定の超高層住宅は全国で450棟、約14万戸(不動産経済研究所調査)におよび、これは前年までに竣工した全戸数をはるかに上回る。特にその数が集中する首都圏では、新規分譲される住戸の5戸に1戸は超高層という試算もある。
日本の超高層住宅の端緒は、1979年に完成した芦屋浜高層住宅である。中高層混在の巨大団地として計画され、各棟および全体が、中高層住宅に典型的な板状ボリュームを踏襲している。それに対し、90年代から大量供給され始めた超高層住宅は、タワーマンションという名のとおり塔状のボリュームで、単体もしくは数体で計画される。塔状になる理由としては、構造的な偏心が少い、廊下が短く平面的効率性が高い、外装面積が少ない、などが挙げられる。
「塔」は、古来からある建築形式であり、ランドマークとしての象徴性をもつと同時に、類まれな眺望を提供する、すぐれて視覚的な産物である。バルトによれば、塔からの視点は人間の雑踏を風景に変え、場所や目印を確認しながら都市の模型を再構成するよう、知性に読み解きを促すものである。また異境からの侵攻者のように、塔に佇むことは都市と対面し挑戦し、それを所有することである、とも彼は指摘している。
住むことの変質
その塔という建築形式が住居に採用され、日常生活の場が、特権的な眺望と象徴性をもつものとなった。1989年の佃のリバーシティ21の成功は、風で洗濯物が干せない、外出に時間がかかるなどのマイナス要素を認めつつも、塔状の集合住宅が高い不動産的価値を持つことを知らしめた。
通常、住居は外部と様々に関わる。採光、通風はもちろん、匂いや音による気配といったものも重要な要素である。上空では、地上の匂いはもちろん、音も届かず捨象され、その代わりにパノラマ的視界が用意される。視覚に極端に優位性が与えられた環境といえる。
最近の超高層住宅は、かつての集合住宅が目指した健康的で光あふれる住居というより、夜の質を重視した、都心の高級ホテルのインテリアに近いものが多い。大規模なものでは、コンシェルジュと呼ばれる管理人が常駐し、クリーニングやマッサージなどのサービスや、フィットネスジムやスカイラウンジなどの施設などが用意されている。住み手はホテルを模した生活の場、日常と非日常の境界が曖昧な場で、都市を鑑賞し所有する。エッフェル塔からの旅行者の視線についての、バルトの指摘とも符号する。
コルビュジェのヴォワザン計画は、10数棟の超高層が良くも悪くも均質な場を張っていた。マンハッタンは、都市全体が立体化している。これらと、低層と中層・高層と混在する日本の超高層住宅とはかなり様相を異にする。渾然一体の余白の少ない都市空間のなかで、孤高な塔としての超高層住宅が、周囲からの差別化を志向するという特異な状況を呈している。これは日照問題はじめ、周辺の一般住宅街や商店街との様々な軋轢、学校など公共施設のキャパシティの問題など、周囲との関係において検討必要な様々な問題を呼び寄せる。超高層の数が増えることで、今後は塔としての属性が失われ、象徴性も薄らぎ、眺望も互いに妨害しあうような事態もありうるだろう。果たして、「塔」ならざる超高層住宅は可能であろうか。