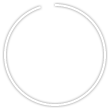nav
aside
私のスケール感
苔と松
学生の頃訪れた、京都のある寺院で、美しく手入れされた杉苔に目を引かれた。 その名通り、数センチの杉林のような苔の群生に見入っていると、そばに生えている人の背丈ほどの小ぶりの松が、とてつもない巨木のように感じられた。 それだけでなく、杉苔の群生と、何本かの若い松、そして林立する大きな松の木が3段階の相似を成し、その先に拡がる大地や空に広がりを感じると同時に、 見えないほどの小さな世界のイメージが想起する不思議な感覚にとらえられた。その後、世界の中で、自分自身がこの大きさであることの確かさや安堵感を覚えた記憶がある。ふたつのスケール
アルベルト・ジャコメッティは細長い人物像で知られるが、その作風へ至る前からつくられていた、高さ数センチほどの小さな作品群がある。 彼の言葉によれば、人物のもつオーラの表現を目指すうちに、彫刻はどんどん小さくなっていったという。 四角い台座は、小さな人物と質感が同じでありながら、アンバランスなほど分厚く量感があり、見る人は、削り出されたような人型の周囲の不思議な密度のある空間に、引き込まれてしまう。一方、地面から伸びた植物のような作品群は、人と同じ背丈の作品であっても、その特異な細さによって実際以上に背が高くも感じる。 単体でも独特な雰囲気をまとっているが、それらが仰ぎ見るほどの高さにまで引き延ばされ、複数配置されると、明らかに特異なスケールの場が作り出される。
空間に意識的だった作家のふたつの系譜からも、小さいということと、大きいということには、何か重要な意味があるような気がして、考えてみたいと思っていた。
小さいこと
実物を何分の一かで再現するミニチュアは、人形や乗物など、世界中で様々な対象で作られていて、生活を再現するドールハウスも、ずいぶん古くからつくられている。 建築家のつくる模型と違って、ドールハウスでは、建物だけでなく家具や食器などの小物類も詳しくつくり込まれる。 ちいさきものはみなうつくし、とした枕草子にも、ひな人形の道具を含む、小さなもの描写が細かく書かれ、小さく詳細なものに向かう時の視覚の解像度が上がることが、 いかに人の喜びを伴うものであるかがうかがえる。1分の1でのリアリティ
1/12の縮尺が多いドールハウスのなかに、煉瓦タイルがあれば、それは幅2センチ高さ1センチほどになる。 これとほぼ同じ大きさで、実際の建物に用いるためのモザイクタイルがあるのだが、私がそれに惹かれている。それは、横長のプロポーションと色調から、一見小さな煉瓦のようにも見えるのだが、実はベージュの大理石でできている。 もし、この大きさで、本物の煉瓦と同じように土を焼いて作ると、実際に使えば簡単に割れてしまうだろう。 ひとつひとつ焼くのも非経済的である。だから、土は、この大きさでこの形を作るのに適した素材ではなく、もし作ったとしても、この大きさにおける素材の根拠が弱い。 それに対して、大理石を切り出す際に生まれる端材をラフにカットすることでこの形をつくれば、素材としての強度をもち、経済性も満たしながら、大きさに合った質感を実現する。 本物の煉瓦との相似的な関係によって、縮小されたような可愛らしさを持ちながら、一方で、1分の1における、その大きさと素材の根拠をもつからこそ、ミニチュアにも、 一般のモザイクタイルにもない、密度をもっているように思う。
同じような密度は、茶室にも現れている。障子の桟や床柱の細さ、網代天井などの素材の緻密さ、にじり口の小ささにみるように、 部材寸法と質感および空間は、一般的な建築よりも数段縮小されながらも、同時に、実際の使用に耐えるという観点から、 ぎりぎりのところで根拠づけられている。小ささと、1分の1でのリアリティの共存こそが、人を厳粛な気持ちに導き、 誰もが茶道という行為を受け入れる空間の質を生んでいると思う。
大きいこと
西欧の教会、東洋の大仏など、祈りに関わるものはしばしば大きい。日常の風景では経験しない大きさというだけでなく、それらの大きさは把握しにくいようにできている。 教会のアーチやヴォールトの曲面は、フラットな天井より高さを測りにくいし、屋内の仏像は、背面の壁や柱などとの比較によって大きさが把握されないよう、 光背によって縁が切られている。西欧の代表的な教会の圧倒的な高さの中に身を置くと誰でも、その大きな空間を見上げながら、しばらくそこに佇みたくなる。 時に跪いて、祈りの姿勢を真似てみたいと思うかもしれない。私が思うに、それは必ずしも特定の宗教に対する信仰心からではなく、ある風景に面する時と共通する、 身体感覚に基づく畏れのようなものではないかと思う。大きな対象に向かうことで、相対的に自身の身体の大きさを知るような、内省的であると同時に開放的な感覚。 対象によって、畏怖や畏敬、解放感などの感情につながる手前の感覚がによって、多くの人間を行為に導く何かが生まれているのだと思う。
同時に、教会を巡って気付くのは、小さな無名の教会でも、程度の差こそあれ、同じ感覚を抱けるということである。 そしてそれは、教会に限らず、例えば学校や住宅でも起こりうることである。
スケールのデザイン
ヴァレリオ・オルジャッティの設計したパスペルの小学校は、矩形の平面の中に、少しだけ角度が振られて教室が置かれている。 その結果、廊下は、かすかにパースが歪んでいる。教室の内壁の素朴な木仕上と対照的に、廊下や階段はコンクリート打ち放しである。 打ち放しの特徴であるPコンの跡は消されてほとんど見えず、一方で床および天井と壁の取り合い部には深い目地が切られているため、壁は一塊の石のようである。 これによって、もともと高めの天井高は、より高く感じられる。同じくコンクリートの天井と床は、足音を長く響かせ、体感のスケールをまた少し広げる。驚いたことに、教室で大騒ぎをしている子供たちは、廊下へ出ると急に静かになり、足音を忍ばせて歩き、廊下の窓辺に腰かけて、 大人びた節度ある声で語り合う。この小さな学校の廊下は、教室との対比と、スケールに関わるいくつかの要素のコントロールによって、教会の大きさと通ずる質を獲得している。
スケールのずれによる、世界とのつながり
私たちが設計という行為で行っていることは、空間の配置と輪郭を定め、部分と全体の関係を考え、開口を穿ち、質感を与えることである。 配置は外部空間のスケールを規定し、上に見たように質感にもスケールがあるとすると、建築で扱う対象のすべてはスケールに関わるといえる。 それらを少しずつコントロールすることで、その相互の関係でさまざまな状況を生み出すことができる。エドマンド・バーク*は、古典的な美とは、小ささ、僅かさ、繊細さから生まれ、近代的な美しさである崇高とは、高さであり、曖昧さと欠如からもたらされると書いた。 それぞれの美しさが、今日、どのような意義をもつかを議論する素養はないが、物の側から見れば、それぞれが小ささいことと、大きいことというスケールを起点として、 身体の内に響く何かをかたちづくることが可能であると示唆してくれてもいる。
繊細な小さな世界をのぞき込む時の喜びと、大きなものに向かい合うことで生じる内省的な感覚は、共に、身体と対象の大きさのずれによって生まれるものであり、 これらが、人と建築との関係をつくるひとつの手掛かりになる。両極端な方向性を目指すことにはそれほど可能性を感じないが、建築の経験の中に、 小さいことと大きいこと、あるいは、小さいと同時に大きいこと、すなわちスケールのズレをつくること、それにより、身体感が冴え、すこしだけクリアに世界が立ち現れる。 そんな建築に惹かれる。
* 英国の哲学者、政治家。英国で最初に美学を体系化したとしても知られる。